暗号資産、2つに分けて規制か──金融庁が「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」ディスカッション・ペーパーを公表
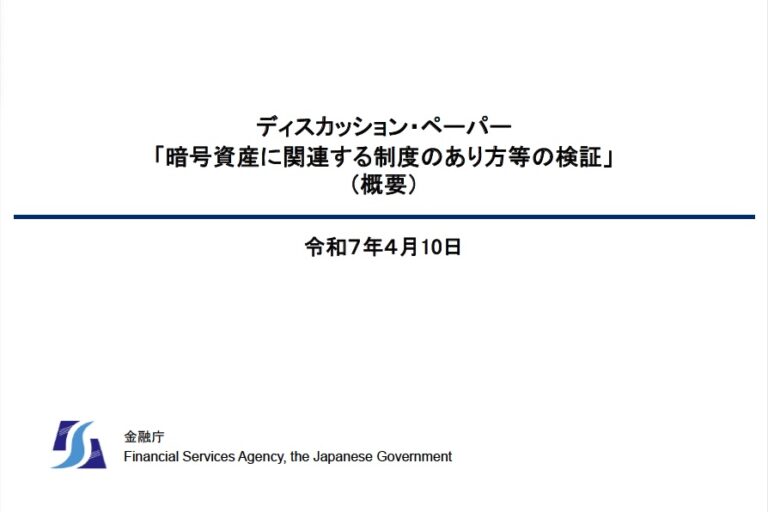
暗号資産(仮想通貨)は、金融商品取引法(金商法)の枠組みの中で、2つに分けて規制されることになりそうだ。
金融庁は4月10日、「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」ディスカッション・ペーパーを公表した。
2024年12月、与党税制改正大綱が「暗号資産取引に係る税制については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ」と記したことを受けて、金融庁は暗号資産に関連する制度のあり方等について非公開の勉強会を開催し、検証を続けてきた。今回公表されたディスカッション・ペーパーは、その検証結果を整理したものだ。
詳細は、金融庁のWebサイトからPDFをダウンロードして、確認してほしい。
「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証(ディスカッション・ペーパー本文)」と「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証(概要)」が公開されている。
ディスカッション・ペーパーは、30ページにわたるが、重要な箇所は「Ⅲ. 規制見直しの基本的な考え方」だ。ここではまず、総論として、以下のように記されている。
「こうした課題は伝統的に金商法が対処してきた問題と親和性があるため、金商法の仕組みやエンフォースメントを活用することも選択肢の一つと考えられる。このような金商法に基づく対処を行うことは、利用者保護等を通じて、暗号資産の支払手段としての機能を高める観点からも有用であると考えられるのではないか」
さらに、規制見直しを検討する際には、暗号資産を2つに分けて検討することが適当ではないか、としている。以下の2つだ。
資金調達・事業活動型暗号資産(類型①):暗号資産が資金調達の手段として発行され、その調達資金がプロジェクト・イベント・コミュニティ活動等に利用される暗号資産(例:一部のユーティリティ・トークン)。
○非資金調達・非事業活動型暗号資産(類型②):類型①に該当しない暗号資産(例:ビットコインやイーサ等)。

暗号資産に関する制度改正の経緯や大枠については、4月3日にブロックチェーン推進協会(BCCC)が開催した “自民党web3WGによる「暗号資産を新たなアセットクラスに〜暗号資産に関する制度改正案」&金融庁提出の「資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」について緊急解説” のレポート記事で伝えた。
関連記事:ビットコイン、金商法での位置づけはどうなる──増田弁護士、尾登弁護士が解説【ブロックチェーン推進協会がセミナー開催】
この記事では、「暗号資産の「新規発行」については、考え方が示されているものの、既存の暗号資産、象徴的に言えば「ビットコインをどう扱うのか?」については、改正案には直接示されていない」と伝えたが、金融庁の検証は、この点にまで踏み込んだ形だ。
5月10日まで意見募集
今回の公表資料が「ディスカッション・ペーパー」と名付けられていることからわかるように、金融庁では、検証内容に対する意見を募集している。詳細は金融庁Webサイトの発表ページに記されている。
2025年1月31日に開催された衆議院予算委員会で、自民党デジタル社会推進本部web3ワーキンググループを主導する塩崎彰久議員の質問に対して、加藤勝信財務大臣は「2025年6月末を目処」に制度の検証を行うと述べていた。
ディスカッション・ペーパーの公表は、6月末に向けて、大きな山を1つ越えたと言えるだろう。
|文:増田隆幸
|画像:ディスカッション・ペーパー「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」(概要)の表紙