仮想通貨取引にかかる税金は?| 税金の計算方法から確定申告まで徹底解説
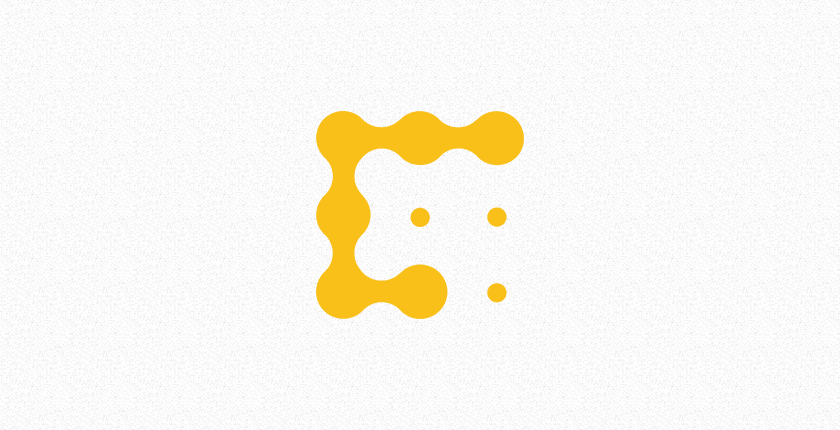
仮想通貨で取引を行うにあたって気になるのが税金についてだと思う。
「仮想通貨の取引にかかる税金は何パーセント?」
「利益の計算方法は?」
「確定申告はしないとバレる?」
この記事では、暗号資産(仮想通貨)の税金や計算方法、確定申告のタイミング、対策について詳しく解説する。
後半では実際に税金のシミュレーションも行っているため、仮想通貨で取引をしている方は、参考にしてほしい。
CoinDeskJapan推奨|おすすめの国内仮想通貨取引所3選
| 取引所名 | 特徴 |
|---|---|
 coincheck | 【500円の少額投資から試せる!】 ◆国内の暗号資産アプリダウンロード数.No1 ◆銘柄数も最大級 、手数料も安い ▷無料で口座開設する◁ |
 bitbank | 【たくさんの銘柄で取引する人向け】 ◆40種類以上の銘柄を用意 ◆1万円以上の入金で現金1,000円獲得 ▷無料で口座開設する◁ |
 SBI VC トレード | 【安心安全な環境で取引したい人向け】 ◆SBIグループの100%子会社で、セキュリティが安心 ◆各種手数料無料 ▷無料で口座開設する◁ |
仮想通貨取引の利益には税金はかかる?
まずは、暗号資産(仮想通貨)通貨取引の利益に税金はかかるのかを解説していく。
暗号資産(仮想通貨)を保有しているのみであれば確定申告は不要
暗号資産(仮想通貨)を保有しているだけの場合、確定申告は不要だ。
もし、購入した時に比べ、暗号資産(仮想通貨)の金額が上がり、含み益となっても所有しているだけであれば税金はかからない。
しかし、暗号資産(仮想通貨)の年間利益が20万円を超える場合は、確定申告が必要となる。
まとめると、保有しているだけでは利益が発生しないため、申告の義務は生じないということだ。
ただ、含み益が出ている状態で売却や換金、交換すると課税の対象となることがあるので注意しよう。
給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
国税庁
給与所得を得ているサラリーマンの場合、雑所得が年間で20万円を超えると確定申告が必要
仮想通貨取引の利益は雑所得に分類されるため、給与所得を得ているサラリーマンは、年間で雑所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となる。
雑所得とは、給与や事業所得以外の所得を指し、具体的には副業の収入、フリーランスの報酬、株式の配当、宝くじの当選金などが含まれる。
なぜなら、会社に勤めている方は源泉徴収で給与分の納税が済んでいるため、暗号資産(仮想通貨)で得た利益を申告し、納税しなければならないからだ。
ただ、利益が20万円以下の場合や暗号資産(仮想通貨)を保有しているだけの場合は確定申告の必要はなく、課税もされない。
下記に課税される所得額と税率をまとめたので、参考にしてみてほしい。
| 課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
自分の所得額に応じて税率は変動するので、各自で正確に確認することが重要だ。
仮想通貨(暗号資産)取引による収入は雑所得として計算される
雑所得は、給与所得など他の所得と合わせた全額に納税しなければならない総合課税の対象だ。
先ほども軽く触れたが、仮想通貨取引による収入は雑所得として扱われる。
そのため、仮想通貨の利益が大きくなればなるほど、税金は高くなり、所得税に課される税率は5%〜45%となっている。

さらに雑所得には、一律して10%の住民税が課され、金額によっては復興特別所得税が合計され、最大税率は55%。
住民税は、雑所得が20万円以下であっても雑所得にあたる利益が出た時点で課税され、金額によって変わることなく一律10%だ。
一方で、FXや株式の譲渡で得た所得は申告分離課税となり、ほかの所得とは別で計算される。
仮想通貨とは、税率の計算方法が異なるので覚えておこう。
法人で仮想通貨(暗号資産)取引を行った場合は?
個人で取引するのも、法人化して取引を行うのも、取引環境に違いはありません。
ただ、法人化することで税金の上限を下げられたり、経費計上できる項目が増える、他の所得との損益通算ができるなどのメリットがある。
一方で、含み益も課税対象となる、会社の維持費用が必要になるなどもデメリットも存在する。
以下に法人化を検討するボーダーラインやメリット、デメリットについてまとめた。
仮想通貨取引での所得が800万円以上の個人は法人化で節税できる可能性が高い
暗号資産(仮想通貨)で年間800万円以上の利益が上がっている場合は、個人で取引を行うよりも法人化したほうが節税できる可能性が高い。
なぜなら、所得税は累進課税となっており、所得に応じて5%~45%の税金を支払わなければならない。
累進課税とは、課税対象の所得や財産が増えれば増えるほど税率が上昇していく仕組みだ。
しかし、ある一定のラインを超えると税率は23.3%と低率される。
資本金により多少の違いはあるが、ある一定のラインというのが、だいたい800万円というわけだ。
上記に方法化するメリット、デメリットをまとめた。
次は、メリットとデメリットをそれぞれ解説していく。
法人で暗号資産(仮想通貨)取引を行うメリット
法人化して暗号資産(仮想通貨)取引を行うメリットは下の通りだ。
法人化すると個人で取引を行うよりも税負担を軽減することが可能だ。
個人では仮想通貨の利益は雑所得扱いになり最大税率は45% 。
対して、法人化すると最大税率は23.2%となっているため、多く稼ぐ場合は法人化すると節税できるというわけだ。
また、厚生年金に加入可能で、社会的信用度もあがる。
さらに仮想通貨取引を個人で行うと収入は雑所得扱いになるが、法人化すると事業所得に区分されるため、他の所得と損益通算することができる。
赤字を最大10年繰り越すことができるので、長い目で見れば赤字を挽回できるチャンスがあるのもメリットだ。
法人で暗号資産(仮想通貨)取引を行うデメリット
下に法人化して仮想通貨取引を行うデメリットをもう一度、記載していく。
個人の場合、含み益は課税対象にはならないが、法人化すると会計基準が個人とは異なるため、決算時には含み益も課税対象となるのがデメリットの1つだ。
また、法人化するにあたって会社を設立するのに定款認証手数料や収入印紙代、設立登記にかかる費用などまとまった費用が必要となる。
さらに法人化したことによって法人税や法人登録可能なオフィスの契約金など固定費用がかかる。
他にも法人化する際に法人名義での銀行口座が必要となるが、暗号資産(仮想通貨)取引が目的の事業である場合、安定した収入を証明するのが難しいので、銀行口座の審査が厳しくなるのもデメリットだ。
暗号資産(仮想通貨)取引による所得の計算方法
次は、仮想通貨取引による所得の計算方法を2つ紹介していく。
移動平均法
移動平均法は、仮想通貨を購入する幾度、取得価額を計算する方法だ。
取引の度に計算するため手間がかかるが、その分実際の取引状況に近い形での取得価額の把握が可能。
また、年度の途中でもすぐに見積もりを確認できるのがメリットである。
総平均法
総平均法は、1年を通して売買した暗号資産の全額を合算し、平均取得価額を算出する方法だ。
利用している取引事業者が発行する年間取引報告書を国税庁が用意している計算書に転記するだけなので、簡単に計算できる。
しかし、年度の途中で所得金額の見積もりを出しにくいのがデメリットだ。
仮想通貨取引で所得が発生する(課税対象となる)ケース
次は、暗号資産取引で所得が発生するケースについてまとめた。
暗号資産(仮想通貨)を売却したケース
保有している暗号資産(仮想通貨)を売却し、利益がでると所得が発生する。
たとえは、ビットコイン(Bitcoin)を2万円で購入し、4万円で売却すると差し引いた2万円が所得となる。
ただ、保有している暗号資産(仮想通貨)の価額が上昇し、含み益が発生したとしても、保有しているだけなら所得は発生しない。
しかし、法人の場合は個人同様に雑所得扱いにはならないため、含み益も所得に含まれる。
暗号資産(仮想通貨)を決済手段として利用したケース
暗号資産(仮想通貨)を決済手段として利用した時点で、所得時の金額が上回っていれは所得が発生する。
なぜなら、暗号資産(仮想通貨)を決済手段として利用することは、暗号資産(仮想通貨)を一度売却し、商品やサービスを購入したとみなされるからだ。
たとえば、ビットコイン(Bitcoin)を1BTC=30万円で購入し、商品やサービスを1BTC=50万円の時に購入すると差額の20万円が所得となる。
差額の20万円が利益とみなされ、課税される。
このように購入時よりも価格が上昇した暗号資産(仮想通貨)を決済手段として使用した場合は、納税義務が発生するというわけだ。
仮想通貨を別の銘柄の仮想通貨に交換したケース
暗号資産(仮想通貨)は、商品やサービスを購入することはもちろん、他の暗号資産(仮想通貨)と交換することも可能だ。
そのため、先ほどのケースと同様、含み益がある暗号資産(仮想通貨)と他の仮想通貨を交換し、利益が出た場合に課税対象となる。
実際に日本円に換金していなくても、暗号資産(仮想通貨)同士の交換で利益が発生した場合には納税義務が発生するので注意しよう。
また、暗号資産の交換は売却と同様に扱われるため、取引履歴を正確に記録し、必要な情報を整理しておくことが重要となる。
税務署からの問い合わせに備え、適切な記録を保管し、暗号資産(仮想通貨)の取引を行う際は税務面にも十分注意を払うことが求められる。
暗号資産(仮想通貨)を贈与されたケース
暗号資産(仮想通貨)を無料で贈与されたケースも所得となり、課税対象となる。
たとえば、業者で行っているボーナスやプレゼントキャンペーンなどで付与されるなど。
暗号資産(仮想通貨)の無料プレゼントは、付与された時点での価額がそのまま利益として扱われる。
また、プレゼントされた暗号資産(仮想通貨)を売却する際、価額が上昇していれば、増額した分も収益となるので注意しよう。
マイニング・ステーキング・レンディングなどで暗号資産(仮想通貨)を取得したケース
マイニングやステーキング、レンディングなどで暗号資産(仮想通貨)を取得し、利益が発生した場合、必要経費を差し引いた額が所得となる。
マイニングとは、暗号資産(仮想通貨)の売買取引を記録する作業で、作業の報酬として暗号資産(仮想通貨)を得る仕組みのことだ。
ステーキングとは、特定の暗号資産(仮想通貨)を保有して報酬を得ることで、レンディングは保有している仮想通貨を第三者に貸し付けて利息を得る仕組みのことを指す。
いずれの手段も利益が発生した時点で所得となり、報酬の評価額は、受け取った時点の時価で計算される。
以上のように、マイニング、ステーキング、レンディングによって取得した暗号資産(仮想通貨)は、いずれも課税対象となる。
税務署からの指摘を避けるためにも、暗号資産(仮想通貨)の取引や取得に関しては、税務上の取り扱いを十分に理解し、適切に申告することが重要だ。
暗号資産(仮想通貨)取引の取得の確定申告方法
次に仮想通貨取引の取得の確定申告方法について解説していく。
まずは、利用している取引所から年間の取引報告書を入手する。
次に、先ほど入手した年間取引報告書をもとに計算書を作成しよう。
計算書を作成したら、確定申告書に内容を転記する。
確定申告書は書面で作成・提出することはもちろん、E-Taxソフトで作成・提出することも可能だ。
確定申告書に内容を転記したら、税務署に提出する。
提出する際には以下の書類が必要となる。
- 確定申告書
- 銀行口座の情報
- マイナンバーカード
- 源泉微収票
税務署に書類を提出し、無事に通ったら所得税を納付して完了。
後ほど詳しく解説していくが、確定申告を怠ると増税される可能性があるので必ず確定申告を行おう。
仮想通貨取引の利益を確定申告しないとバレる?
仮想通貨の取引はすべて記録されいるため、確定申告をせずにいると税務署にバレる可能性は高い。
海外取引所を利用している場合、日本の税務署にはバレないのでは?と思いがちだが、日本は世界各国と租税条約を結んでいる。
| アメリカ | 署名日:2003年11月6日 発効日:2004年月30日 |
| イギリス | 署名日:2006年2月2日 発効日:2006年10月12日 |
| イタリア | 署名日:1969年3月20日 発効日:1973年3月17日 |
| インド | 署名日:1989年3月7日 発効日:1989年12月29日 |
| オーストラリア | 署名日:2008年1月31日 発効日:2008年12月3日 |
| カナダ | 署名日:1986年5月7日 発効日:1987年11月14日 |
| 韓国 | 署名日:1998年10月8日 発効日:1999年11月22日 |
| シンガポール | 署名日:1994年4月9日 発効日:1995年4月28日 |
| スペイン | 署名日:2018年10月16日 発効日:2021年5月1日 |
| ドイツ | 署名日:2015年12月17日 発効日:2016年10月28日 |
今回は記載していないが、他にも日本と租税条約を結んでいる国や地域はあり、全部で143ヶ国ある。
そもそも租税条約とは、二重課税の排除や脱税、租税回避の防止を目的とした条約だ。
租税条約により、海外の銀行を利用した場合でも日本の税務署は海外の銀行情報を知ることができる。
そのため、申告していないことがバレる可能性が高く、たとえ個人だとしても大規模な税務調査を行うことがある。
暗号資産(仮想通貨)の取得について確定申告をしなかった場合のペナルティは?
暗号資産(仮想通貨)で得た利益を確定申告せず、納税しなかった場合、重いペナルティが課されてしまう。
重いペナルティとは、未納の税金を納めるだけでなく、延滞税や利子税、加算税が追加された税金を納めなければならない。
また、悪質だと判断された場合には、先ほどの追加税に加え、重加算税が加算される可能性もある。
税金の未納がバレると本来納税する金額にさらに上乗せの形で納税金額が増えるので、確定申告は忘れずに行おう。
仮想通貨取引の確定申告における注意点
次に、暗号資産(仮想通貨)の確定申告における注意点についてまとめた。
仮想通貨取引の所得は給与所得と損益通算できない
原則、仮想通貨取引の所得は雑所得に該当するため、給与所得と損益通算することができない。
損益通算とは、損失がでた所得を他の利益が出ている所得から差し引くことを指す。
たとえば、不動産投資をして100万円の損失がでた場合、他の事業の黒字から損失分の100万円を差し引いて税金を計算することができる。
しかし、仮想通貨は損益通算ができないため、たとえ損失が出たとしても他の利益から差し引くことができない。
また、暗号資産(仮想通貨)で出た損失は繰越不可なので、翌年以降の利益と相殺することもできない。
そのため、仮想通貨取引を行う投資家は税金の負担を考慮しながら取引を行う必要がある。
法人であれば事業所得との損益通算が可能
原則、仮想通貨の所得は損益通算できないが、法人であれば、事業所得との損益通算が可能。
なぜなら、法人の場合、仮想通貨で出た損益は雑所得ではなく、事業所得に該当するからだ。
また、2018年4月1日以降に開始する事業年度における赤字は最大10年間繰り越すことができる。
そのため、年度毎に大きな損失が出ても、長い目で見れば赤字を取り戻すことも可能だ。
仮想通貨取引の確定申告での経費計上は可能
確定申告の際、仮想通貨所得の売却金額や売却原価を差し引くのはもちろん、手数料や必要経費を経費計上することが可能だ。
経費計上し、利益から差し引いた額が所得となる。
経費として落とせるのは、セミナー代や書籍、コンサルティング代など。
また、仮想通貨取引を行う際に利用するスマホやパソコンも経費として落とすことも可能だが、10万円以上ならば全額をその年の経費とすることができず、減価償却が適用される。
減価償却とは、耐用年数を通じて少しずつ必要経費に計上していくことだ。
また、プライベートでも利用している場合は、仮想通貨の取引に直接要したと認められる部分しか経費として落とせないので注意しよう。
ただし、個人の場合経費計上できる項目が限られる
仮想通貨取引の確定申告で、経費計上は可能だが、法人と個人では経費計上できる項目が異なる。
下にまとめたので、参考にしてほしい。
法人のほうが経費計上できる項目は多く、仮想通貨に関連する出費はだいたい必要経費として認められる。
個人も法人も経費計上する際は、証拠となる書類が必要となるので、必要書類はしっかりとまとめて保管することが大切だ。
仮想通貨取引の確定申告に関するよくある質問
次は、仮想通貨取引の確定申告に関するよくある質問をまとめた。
- ビットコインで500万円稼いだら税金はいくらですか?
-
ビットコインで年間500万円稼いだ場合の税金は、所得税20%と住民税10%で合計70.4万円となる。
ただ、年間500万円稼いだときの税金が70.4万円になるのは、収入がビットコインのみの場合である。
他に収入がある方は、所得控除があるため、500万円の利益すべてに税金がかかるわけではない。
- 仮想通貨で無税はいくらまで?
-
仮想通貨は、雑所得扱いとなり、雑所得が20万円以下であれば課税されない。
また、確定申告の必要もない。
- 仮想通貨の税金はバレないって本当?
-
仮想通貨取引の履歴はすべて記録されているため、無申告はバレてしまう可能性が高い。
無申告が発覚した際には、延滞税や無申告加算税、重加算税など厳しいペナルティが科されることがあるので注意が必要だ。
- 仮想通貨の税金は何パーセント?
-
仮想通貨の税金は、他の所得と合わせて算出される総所得税によって5%〜45% と変わってくる。
さらに住民税や復興所得特別税が加算されるため、最大税率は55%となる。
ただ、仮想通貨取引の利益を含めた雑所得が20万円以下の場合は、税金はかからず、確定申告の必要はない。
まとめ
今回は、仮想通貨(暗号資産)の確定申告についてまとめた。
仮想通貨を保有しているだけなら、含み益になっていても、確定申告する必要はない。
また、仮想通貨の利益が年間20万円以下の場合も確定申告の必要はないが、超えた場合には確定申告の義務があるので忘れずに行おう。
CoinDeskJapan推奨|おすすめの国内仮想通貨取引所3選
| 取引所名 | 特徴 |
|---|---|
 coincheck | 【500円の少額投資から試せる!】 ◆国内の暗号資産アプリダウンロード数.No1 ◆銘柄数も最大級 、手数料も安い ▷無料で口座開設する◁ |
 bitbank | 【たくさんの銘柄で取引する人向け】 ◆40種類以上の銘柄を用意 ◆1万円以上の入金で現金1,000円獲得 ▷無料で口座開設する◁ |
 SBI VC トレード | 【安心安全な環境で取引したい人向け】 ◆SBIグループの100%子会社で、セキュリティが安心 ◆各種手数料無料 ▷無料で口座開設する◁ |
ranking